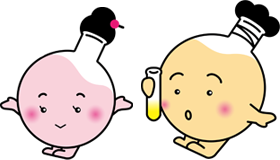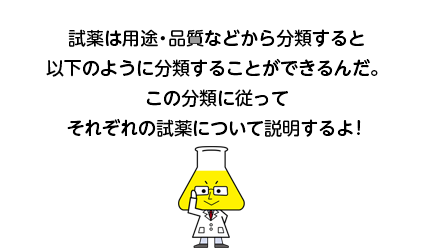
-
一般用途試薬 特級、1級、GR、EP、高純度、精密分析用、化学用、CPなど
-
一般用途試薬としては酸、アルカリ、有機溶剤などに代表される多種類の試薬が存在し、用途を限定せずに、各種用途に(一般的に;forgeneraluse)用いることができる試薬であり、いくつかの等級とそれに応じた規格が設定され、使用者が分析や試験の目的、要求精度および要求純度に応じて適切な等級を選択できる。公定法の試験などで汎用的に用いられる品目については、JISが定められており、品質水準に応じてJIS試薬特級、試薬1級および無等級として区別されている。
JISに含まれない品目またはJISがあっても製造業者がこの規格によらず独自規格で販売する品目は、品質水準に応じて各社によって作成されたA社特級、A社1級、GR、EPなどの等級に分けられているのが一般的である。海外試薬規格には、等級の概念が無く、表2─2に示す規格名称が用いられることが多い。
-
一般用途試薬としては酸、アルカリ、有機溶剤などに代表される多種類の試薬が存在し、用途を限定せずに、各種用途に(一般的に;forgeneraluse)用いることができる試薬であり、いくつかの等級とそれに応じた規格が設定され、使用者が分析や試験の目的、要求精度および要求純度に応じて適切な等級を選択できる。公定法の試験などで汎用的に用いられる品目については、JISが定められており、品質水準に応じてJIS試薬特級、試薬1級および無等級として区別されている。
-
高純度試薬
- 近年の高感度分析技術の進歩は著しく、その過程で数多くの特定用途試薬に対する要求が高まっており、高純度試薬は、ICP質量分析法などで必要とされる試薬である。また、電子工業の高度化に伴い、電子工業用の薬品の基礎として、高純度試薬の位置づけは極めて重要である。現在、代表的な試薬として、過塩素酸、アンモニア水、水酸化ナトリウム溶液、硫酸、2-プロパノール、硝酸、塩酸などが挙げられる。その特徴は、不純物の保証の項目の多さと、規格値が質量分率ppbから質量分率pptの高品位レベルで管理されていることである。
-
特定用途試薬 【機器分析用】高速液体クロマトグラフィー用、ガスクロマトグラフィー用、原子吸光分析用、蛍光分析用、電子顕微鏡用、吸光分析用、核磁気共鳴分光用など
【有害物質および環境汚染物質測定用】有害金属測定用、残留農薬試験用、水質分析用大気汚染物質(オキシダント、窒素酸化物、悪臭など)測定用食品分析用など
【その他】pH標準液用、薄層クロマトグラフィー用など- 試薬は、機器分析をはじめとする各種用途に用いられているが、それぞれの用途により要求される品質が異なり、各用途に適した品質を保証した試薬の供給が行われ、強制法規とも密接に関係していることが多い。
-
(1)機器分析用試薬
- 機器分析技術の著しい発達によって、現在、感度や精度の高い測定が可能となったが、このような測定の高度化に対応して、高純度の試薬に対する需要がますます高まってきている。現在、それぞれの機器分析に最適な試薬として次のようなものが市販されている。
-
高速液体クロマトグラフ用試薬
-
高速液体クロマトグラフィーは、充填剤の改良や機器の高度化、自動化によりガスクロマトグラフィーと同様に高感度で迅速な分析法として広く用いられている。試薬としては、充填剤(充填カラムが一般に用いられている)および移動相として各種の溶媒が使用され、検出方法に合わせ、紫外部吸収、質量分析の適合性、蛍光分光分析の適合性などの項目で、妨害となる成分を極低レベルで保証している。また、測定の際に、分離に影響する水分、試料を分解または変質させる過酸化物、カラムの劣化を早める微粒子についても保証が行われている。充填カラムおよび溶媒は分取用のものも販売されている。
また、イオン性の強い試料の場合、試料イオンと反対の電荷をもつイオンをカウンターイオンとして溶離液に添加しイオン対を形成させることにより親油性固定相への保持を強めて分離できるようにするイオンペアー用試薬も存在する。
代表的な高速液体クロマトグラフィー用試薬の例
種別 試薬例 種 別溶媒 試薬例アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、2-プロパノール、ヘキサン、メタノールなど 種 別イオンペアー試薬 試薬例ペンタンスルホン酸ナトリウム、ヘキサンスルホン酸ナトリウム、ヘプタンスルホン酸ナトリウム、オクタンスルホン酸ナトリウム、トリヘキシルアミン、トリオクチルアミンなど
-
-
ガスクロマトグラフ用試薬
-
ガスクロマトグラフィーは、無機ガスや有機物の分析に広く用いられ、水素炎イオン化型検出器(FID)や電子捕獲型検出器(ECD)などの高感度の検出器が普及し、アルキル水銀、農薬成分の分析などの分野での高感度、高速度分析法となっている。
代表的なガスクロマトグラフィー用試薬の例
種 別 試薬例 種 別標準品 試薬例脂肪酸およびエステル、ステロイド類、炭化水素類、アルコール類、N-ニトロソジメチルアミン、N-ニトロソジイソブチルアミンなど 種 別溶媒 試薬例アセトン、アセトニトリル、メタノールなど 種 別前処理試薬 試薬例 トリメチルシリル化剤(TMS化剤):
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド、クロロトリメチルシランなど
ハロメチルジメチルけい素化剤(HMS化剤):
クロロメチルジメチルクロロシランなど
トリフルオロアセチル化剤(TFA化剤):
トリフルオロ酢酸、N-トリフルオロアセチルイミダゾール
エステル化剤:
三ふっ化ほう素メタノール溶液、塩化水素メタノール溶液、N,N-ジメチルホルムアミドジアルキルアセタール類など
ジアゾメタン発生試薬:
(N-[N-(ニトロソメチルアミノ)メチル]ベンズアルデヒド、N-メチル-N-ニトロソ-p-トルエンスルホンアミド)など
アルキル化剤:
1-アルキル-3-p-トリアゼン類など
試薬としては標準品、溶媒のほか、カルボン酸のメチル化およびアルキル化剤、糖、アミノ酸、ステロイドなどのトリメチルシリル(TMS)化剤のように高い揮発性をもつ誘導体に導き分析可能とする試料の前処理試薬が市販されている。通常、これらの試薬はガスクロマトグラフィーで不純物ピークなどについて保証されている。
-
-
原子吸光分析用試薬
-
原子吸光分析法は、微量の金属類の定量法として広く用いられている。この方法の特徴は高感度、高選択性で操作が簡単という点であり、水、土壌、生物試料中の重金属類の重要な分析法の一つとして用いられている。
この分析方法を用いることによって重金属の微量分析、特に水銀では従来法に比べて約百倍もの高感度分析が可能となった。このため、この分析に用いる試薬としてはこのような不純物の含有量が極めて少ない試薬が供給されている。
さらに、従来のフレームを用いる原子吸光分析より高感度に測定できる電気加熱式(フレームレス)原子吸光分析にも使用できるような高品質の酸、アルカリ類、その他の試薬が市販されている。
代表的な原子吸光分析用試薬の例
種別 試薬例 種 別酸、アルカリ 試薬例アンモニア水、塩酸、過塩素酸、硝酸、硫酸など 種 別酸化剤、還元剤 試薬例亜鉛粉末、塩化ヒドロキシルアンモニウム、過酸化水素、過マンガン酸カリウムなど 種 別干渉抑制試薬 試薬例塩化ストロンチウム、塩化ランタン、塩化リチウム、くえん酸二アンモニウム、酒石酸カリウムナトリウムなど 種 別抽出用溶媒 試薬例酢酸n-ブチル、4-メチル2-ペンタノンなど 種 別キレート剤 試薬例ジエチルジチオカルバミン酸アンモニウム、ピロリジンジチオカルバミン酸アンモニウム、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム、ジチゾンなど 種 別マトリックス修飾剤 試薬例パラジウム-マグネシウムマトリックス修飾剤、ニッケルマトリックス修飾剤など
-
-
蛍光分析用試薬
-
蛍光分析法は感度が高いこと、選択性に優れていることから微量成分の定量に使用されるようになり、現在では金属分析から生化学、特にアミノ酸の分析、たんぱく質の高次構造の研究、残基の修飾および定量などに広く用いられている。試薬としては、蛍光修飾試薬(蛍光ラベル化剤)および溶媒を必要とする。この蛍光修飾試薬は、その試薬自身は蛍光をもたないが、特定の化合物と結合することにより強い蛍光性を示す試薬である。
代表的な蛍光分析用試薬の例
種別 試薬例 種 別無蛍光溶媒 試薬例2-プロパノール、2-メチル-1-プロパノール、シクロヘキサン、N,N-ジメチルホルムアミド、ヘキサン、メタノールなど また、蛍光分析用の各種溶媒は蛍光を発しないか、または極めて低蛍光になるように精製され、例えば250nm~600nmで不純蛍光ピークが硫酸キニーネ1ppbの発する蛍光以下に保証されたものなどが市販されている。
-
-
電子顕微鏡用試薬
-
包埋剤、硬化剤、加速剤、固定剤などの電子顕微鏡用超薄切片の作製から染色までの一連の必要試薬が電子顕微鏡用として市販されている。
代表的な電子顕微鏡用試薬の例
種別 試薬例 種 別包埋剤 試薬例エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテルなど 種 別硬化剤 試薬例1-デセニルこはく酸、メチルナジン酸、ノネニルこはく酸など 種 別加速剤 試薬例2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノールなど 種 別固定剤 試薬例グルタルアルデヒド溶液、オスミウム酸など 種 別その他 試薬例γ-コリジン(2,4,6-トリメチルピリジン)、ゼラチンカプセルなど
-
-
液体シンチレーション用試薬
-
有機液体シンチレーター法に使用する試薬。即ち放射線により発光する試薬(第1次溶質)、その発光をさらに最高感度にシフトさせる試薬(第2次溶質)やこれらの溶質をよく溶かし、よく発光させる溶媒と調製液とが市販されている。これらの試薬は放射線により発光を妨害する物質を含まない高純度試薬である。溶媒については、計数効率を低下させる測定波長での光を発する不純物、可視部および紫外部で着色する物質、過酸化物について品位が保証されている。
代表的な液体シンチレーション用試薬の例
種別 試薬例 種 別第1次溶質 試薬例p-テルフェニル、DPO1)、ブチル-PBD2)、BBOT3)、ナフタレンなど 種 別第2次溶質 試薬例POPOP4)、ジメチルPOPOP5)、Bis-MSB6)など 種 別溶媒 試薬例トルエン、1,4-ジオキサン、1,2-ジメトキシエタンなど 種 別その他 試薬例シンチレーターカクテル、2-アミノエタノールなど ※1)DPO:2,5-ジフェニルオキサゾール
2)ブチル-PBD:2-(4-tert-ブチルフェニル)-5-(4-ビフェニリル)-1,3,4-オキサジアゾール
3)BBOT:2,5-ビス[2-(5-tert-ブチルベンゾオキサゾリル)]チオフェン
4)POPOP:1,4-ビス[2-(5-フェニルオキサゾリル)]ベンゼン
5)ジメチルPOPOP:1,4-ビス(4-メチル-5-フェニルオキサゾリル)ベンゼン
6)Bis-MSB:1,4-ビス(メチルスチリル)ベンゼン
-
-
吸光分析用試薬
-
可視部および紫外部吸光度法(吸光光度法)は広範囲で用いられる分析法であり、紫外部吸収スペクトルの測定に使用される溶媒は紫外部に吸収を有する不純物を極力含まないことが要求され、測定を妨害する吸収をもつ不純物が少ないことが保証されている。また、赤外吸収スペクトル用には、測定試料を希釈し、錠剤を成型する試薬が存在する。
代表的な吸光分析用試薬の例
種別 試薬例 種 別紫外線吸収測定用 試薬例アセトン、アセトニトリル、ベンゼン、クロロホルム、シクロヘキサン、酢酸エチル、ヘプタン、ヘキサン、メタノール、2,2,4-トリメチルペンタン、トルエン、テトラヒドロフラン、N,N-ジメチルホルムアミド、ジクロロメタン、2-プロパノールなど 種 別赤外線吸収測定用 試薬例臭化カリウム、塩化ナトリウムなど
-
-
核磁気共鳴分光用試薬
-
核磁気共鳴分光法は、定性試験にとどまらず、定量分析にも用いられるが、そこで使用される試薬は、測定の妨害が少ない重水素化された溶媒や定量試験で用いられる内標準などが主流である。
代表的な核磁気共鳴分光用試薬の例
種別 試薬例 種 別溶媒 試薬例クロロホルム-d、メタノール-d4、ジメチルスルホキシド-d6、水-d2など 種 別シフト試薬 試薬例Eu-DPM1)、Pr-FOD2)など 種 別内標準 試薬例ジメチルスルホン、安息香酸、マレイン酸、1,4-BTMSB3)-d4など 種 別スピンラベル化剤 試薬例4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシルなど ※1)Eu-DPM:トリス(ジピバロイルメタナト)ユウロピウム
2)Pr-FOD:トリス(ヘプタフルオロブタノイルピバロイルメタナト)プラセオジム
3)1,4-BTMSB:1,4-ビス(トリメチルシリル)ベンゼン
-
-
(2)有害物質および環境汚染物質測定用試薬
-
有害物質および環境汚染物質測定試薬は大気、水質、食品など生活環境中にある人体に影響を及ぼす物質を測定するため、それぞれの目的に応じた高純度の品質を保証した特定用途試薬である。
用途名として対象とする測定物質名がつけられているが、その物質の分析法に応じてガスクロマトグラフィー分析法、原子吸光分析法、吸光分析法などの機器分析に使用できる品質のものが市販されている。
有害物質測定では極めて微量の分析が要求されるため、各試験はその方法での検出限界付近で分析を行うことが多く、そのため試薬類は高品質のものが必要とされる。
-
-
(3)有機合成用試薬
-
有機合成技術の進歩により、膨大な数の新規の化学物質がもたらされ、現代の物質文明の発展の基礎となってきた。今日、新しい性質・機能を持つ化合物の創製、分子設計に基づくより精密な合成法の開発、環境へ配慮した有害物質を生成しない化合物の創製等に大きな努力が続けられている。
有機合成用試薬は、農薬、医薬、高分子、機能材料等新規化合物の創製研究、その合成プロセスの研究、あるいは各種有機化合物の性質・機能解明の研究等に用いられる試薬で、合成の出発物質、中間体、反応剤、触媒、溶剤、分離精製剤等、多種の試薬が市販されている。試薬例 試薬例酸化剤・還元剤、縮合剤、ハロゲン化試薬、保護剤、グリニャール試薬、相間移動触媒、高選択的水素化触媒、不斉合成用試薬、光学活性体、光学分割剤、有機金属試薬、重水素化合物・アイソトープラベル化剤、脱水溶剤
-
-
(4)その他の特定用途試薬
-
以上、特定用途試薬について代表的なものを述べてきたが、その他の特定用途試薬の主要なものを次に示す。
種 別 試薬例 種 別pH測定用 試薬例二しゅう酸三水素カリウム二水和物(四しゅう酸カリウム)、フタル酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、りん酸水素二ナトリウム(無水)、四ほう酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム 種 別薄層クロマトグラフ用 または カラムクロマトグラフ用 試薬例 吸着剤
アルミナ、シリカゲル、けいそう土、ポリアミド、酢酸セルロース、TLCプレート
溶媒
アセトン、ベンゼン、1-ブタノール、クロロホルム
活性度検定用
各種色素溶液(テスター)、p-ヒドロキシアゾベンゼン、スダン III
発色試薬
アントロン、ニンヒドリン
その他
蛍光紙、焼きせっこう
種 別非水滴定用 試薬例 溶媒
酢酸、1,4-ジオキサン
標準液
0.1mol/L過塩素酸酢酸溶液、0.1mol/Lカリウムメトキシド、ベンゼン・メタノール溶液
指示薬溶液
アゾバイオレット溶液、クリスタルバイオレット溶液、α-ナフトールベンゼイン溶液
種 別コロイド滴定用 試薬例グリコールキトザン、メチルグリコールキトザン、ポリビニル硫酸カリウム、トルイジンブルー指示薬溶液 種 別石油製品試験用 試薬例アニリン、B重油標準液、ジブチルジスルフィド、テトラリン、デカリン 種 別ぬれ試験用試薬 試薬例ぬれ指数標準液 種 別乳質検査用試薬 試薬例牛乳の細菌汚染度測定試薬(レザズリンの製剤)、2,3,5-トリフェニルテトラゾリウムクロリド
-
-
標準物質・標準液 容量分析用標準物質、pH 標準液、金属標準液、非金属イオン標準液、滴定用溶液など
- 標準物質は、一つ以上の規定特性について、十分均質且つ安定であり、測定プロセスでの使用目的に適するよう作製された物質である。特に認証標準物質(標準物質認証書が付いている標準物質)は、その特性値に計量トレーサビリティがあって不確かさが付随し、化学分析において濃度決定、検量線作成、機器校正、分析手法の妥当性確認等に用いられる。水道水質試験、環境分析や食品分析等のような高い信頼性が必要な分析、輸出入を伴う商取引における第三者への説明の重要性から、認証標準物質を中心とした標準物質の整備・供給が進められている。 また、濃度やpH等が決められた標準液は、機器分析で広く用いられている。これら標準液は、かつては分析者が自分で調製するのが普通であったが、近年は使用者の省力化や計量トレーサビリティの必要性等の観点から、市販品の需要が生じ、試薬製造業者が製造、供給するようになってきている。 機器分析で用いられる金属標準液やpH標準液等は、かつてはそれぞれにJISが制定されていた。例えば、銅標準液(JIS K 0010)、しゅう酸塩pH標準液(JIS K 0018、第1種、第2種が規定)である。しかし、これら多くの標準液に関係するJISは2000年代になって廃止され、市販品の標準物質・標準液は、JCSSやASNITE等の制度に基づいて生産・供給されるものが増えてきている。JCSSは、JapanCalibrationServiceSystemの略で、計量法トレーサビリティ制度ともいう。近年、JCSSに基づく標準液は、多くのJISにおいてその利用が明記されるようになってきた。また、ASNITE(製品評価技術基盤機構認定制度)は、認定制度の一つであり、ISO 17034「標準物質生産者の能力に関する一般要求事項」やISO/IEC17025「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に基づく認定プログラムである。これらの制度に基づく標準物質・標準液の利用は、ユーザーの省力化になるばかりでなく、より信頼性の高い分析を行う上でも欠かせないものとなっている。
-
金属標準液
-
金属標準液は、原子吸光分析や誘導結合プラズマ発光分光分析等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられる。表2─11にJCSSに基づく金属標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。多元素同時分析のために複数の元素を混合した標準液も供給されはじめている。JCSSに基づく標準液の使用がJISに明記されている場合には、JISの記述にしたがって用いる必要がある。JCSSに基づく標準液は、その金属イオンの化学形態(価数等)が必ずしも明確ではなく、その溶媒の種類も多様である。そのため、特に湿式分析に用いる場合には注意を要する。また、必ずしも主成分以外の成分(共存物質)が含まれていないことを保証しているわけではないので、標準液を混合して用いる場合にも注意を要する。JIS K 8001:2017「試薬試験方法通則」には、多くの標準液について、ユーザーが試薬から調製するときの方法が記載されているが、目的に応じて選択することが重要である。
JCSSに基づく金属標準液
亜鉛、アルミニウム、アンチモン、インジウム、カドミウム、カリウム、ガリウム、カルシウム、銀、クロム、コバルト、水銀、すず、ストロンチウム、セシウム、セレン、タリウム、鉄、テルル、銅、ナトリウム、鉛、ニッケル、バナジウム、バリウム、ビスマス、ひ素、ほう素、マグネシウム、マンガン、モリブデン、リチウム、ルビジウム、金属15種混合
-
金属標準液は、原子吸光分析や誘導結合プラズマ発光分光分析等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられる。表2─11にJCSSに基づく金属標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。多元素同時分析のために複数の元素を混合した標準液も供給されはじめている。JCSSに基づく標準液の使用がJISに明記されている場合には、JISの記述にしたがって用いる必要がある。JCSSに基づく標準液は、その金属イオンの化学形態(価数等)が必ずしも明確ではなく、その溶媒の種類も多様である。そのため、特に湿式分析に用いる場合には注意を要する。また、必ずしも主成分以外の成分(共存物質)が含まれていないことを保証しているわけではないので、標準液を混合して用いる場合にも注意を要する。JIS K 8001:2017「試薬試験方法通則」には、多くの標準液について、ユーザーが試薬から調製するときの方法が記載されているが、目的に応じて選択することが重要である。
-
非金属イオン標準液
-
非金属イオン標準液は、イオンクロマトグラフィー等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられる。表2─12にJCSSに基づく非金属イオン標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。近年、JISに明記されることも増えてきているが、金属標準液と同様に、市販品の濃度領域や溶媒等が目的に適していることの確認は重要である。
JCSSに基づく非金属イオン標準液
亜塩素酸イオン、亜硝酸イオン、アンモニウムイオン、塩化物イオン、塩素酸イオン、シアン化物イオン、臭化物イオン、臭素酸イオン、硝酸イオン、ふっ化物イオン、硫酸イオン、りん酸イオン、陰イオン7種混合
-
非金属イオン標準液は、イオンクロマトグラフィー等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられる。表2─12にJCSSに基づく非金属イオン標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。近年、JISに明記されることも増えてきているが、金属標準液と同様に、市販品の濃度領域や溶媒等が目的に適していることの確認は重要である。
-
有機標準液
-
有機標準液は、ガスクロマトグラフィー等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられ、大気、水質、土壌など広範囲な環境分析で利用されている。表2─13にJCSSに基づく有機標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。揮発性有機化合物や環境ホルモンといわれる物質等が整備されている。有機標準液は、その種類も多いことからJCSSではすべてが供給されていないこともあり、試薬製造業者による市販品も多い。
JCSSに基づく有機標準液
o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、cis-1,2-ジクロロエチレン、trans-1,2-ジクロロエチレン、2,4-ジクロロフェノール、1,2-ジクロロプロパン、cis-1,3-ジクロロプロペン、trans-1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジクロロベンゼン、ジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、全有機体炭素、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、トリブロモメタン、トルエン、ビスフェノールA、フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-n-プロピル、フタル酸ジ-n-ヘキシル、フタル酸ジ-n-ペンチル、フタル酸ブチルベンジル、4-n-ブチルフェノール、4-t-ブチルフェノール、ブロモジクロロメタン、4-n-ヘプチルフェノール、ベンゼン、ホルムアルデヒド、4-n-ノニルフェノール、アルキルフェノール類等5種混合、アルキルフェノール類等6種混合、かび臭物質2種混合、揮発性有機化合物23種混合、揮発性有機化合物25種混合、ハロ酢酸4種混合、フェノール類6種混合、フタル酸エステル類8種混合
-
有機標準液は、ガスクロマトグラフィー等の機器分析において、主として検量線の作成に用いられ、大気、水質、土壌など広範囲な環境分析で利用されている。表2─13にJCSSに基づく有機標準液(pH以外の標準液、計量法施行規則第90条第2項)を示した。揮発性有機化合物や環境ホルモンといわれる物質等が整備されている。有機標準液は、その種類も多いことからJCSSではすべてが供給されていないこともあり、試薬製造業者による市販品も多い。
-
pH標準液
-
pHは、酸性、アルカリ性等の液性を定量的に表すのに広く用いられており、pH計を用いてpHを測定するときはpH標準液を用いてpH計の目盛を校正する必要がある。JCSSでは、pH標準液6品目が供給されている(表2─14)。25℃におけるpHの値は、JIS Z 8802:2011「pH測定方法」の認証pH標準液の典型値である。この他、メーカーが独自に調製したものでpH緩衝液として市販されているものがある。
JCSSに基づくpH標準液とpHの典型値(JIS Z 8802:2011)
品目 pHの典型値(25℃) 第1種 第2種 しゅう酸塩pH標準液 1.679 1.68 フタル酸塩pH標準液 4.008 4.01 中性りん酸塩pH標準液 6.865 6.86 りん酸塩pH標準液 7.413 7.41 ほう酸塩pH標準液 9.180 9.18 炭酸塩pH標準液 - 10.01
-
pHは、酸性、アルカリ性等の液性を定量的に表すのに広く用いられており、pH計を用いてpHを測定するときはpH標準液を用いてpH計の目盛を校正する必要がある。JCSSでは、pH標準液6品目が供給されている(表2─14)。25℃におけるpHの値は、JIS Z 8802:2011「pH測定方法」の認証pH標準液の典型値である。この他、メーカーが独自に調製したものでpH緩衝液として市販されているものがある。
-
容量分析用標準物質および滴定用溶液
-
容量分析では、中和滴定用、酸化還元滴定用、沈殿滴定用、錯滴定用等、各種の滴定用溶液が用いられており、これら滴定用溶液の精確な濃度の決定(標定)に容量分析用標準物質が用いられる。これらの物質は、容量分析におけるいわば物差しの役を果たしており、表示されている純度をもとにして物質量、含有量等の数値が決められることになる。
JISでは、JIS K 8005:2016「容量分析用標準物質(追補1)」として表2─15に示す12品目が規定されている。かつては、これ以外にスルファニルアミドおよび三酸化二ひ素が含まれているときがあったが、現在は削除されている。また、炭酸カルシウムとトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンは、2016年の追補1において、利便性と国際対応のために新しく追加された。
これらの容量分析用標準物質は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)がJISによる品質試験を行い、その純度の値付けを行ってきたが、現在は、JIS K8005に規定する方法で値付けされた物質を容量分析用標準物質としている。値付けの方法は、滴定法、電解重量法、重量法および不純物分析法であり、滴定法を用いる場合には、一次標準物質(国際単位系にトレーサブルな容量分析用標準物質の基準)との比較によって決めることとされている。現在、製品評価技術基盤機構認定制度(ASNITE)に基づく容量分析用標準物質として利用可能な認証標準物質を購入することが可能である。また、容量分析用標準物質は、十分に高純度で、その値も精確に決められているため、使用の際には、乾燥条件、最小使用量、有効期限、保管条件等に注意を要する。
容量分析用標準物質の種類
亜鉛、アミド硫酸、塩化ナトリウム、しゅう酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、銅、二クロム酸カリウム、フタル酸水素カリウム、ふっ化ナトリウム、よう素酸カリウム、炭酸カルシウム、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 容量分析で、滴定に用いる液を滴定用溶液という。表2─16は、JIS K 8001:2017「試薬試験方法通則」において標定する滴定用溶液と容量分析用標準物質との関係の例を示したものである。左側の標準物質をもとに、中央に記載されている滴定用溶液が標定できる。右側の滴定用溶液は化学反応の関係から、対応する左側の標準物質で直接標定できないので、中央の滴定用溶液を介して間接的に標定する。JIS K 8001に示した滴定用溶液以外にも、中和滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴定に利用可能な多数の種類・濃度の滴定用溶液が市販されている。一部の滴定用溶液は認定プログラムに基づく認証書が付されており、信頼性の高い溶液を入手可能である。
JIS K 8001:2017に規定する滴定用溶液
容量分析用
標準物質標定しようとする滴定用溶液の例 亜鉛 → 亜鉛溶液 → エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液 → 塩化マグネシウム溶液 → 酢酸亜鉛溶液 → 硝酸鉛(Ⅱ)溶液 → 硝酸ビスマス溶液 アミド硫酸 → 亜硝酸ナトリウム溶液 → 水酸化ナトリウム溶液 → 酢酸 → ナトリウムメトキシド・ベンゼン溶液 → 水酸化カリウム溶液 塩化ナトリウム → 硝酸銀溶液 → チオシアン酸アンモニウム溶液 しゅう酸ナトリウム → 過マンガン酸カリウム溶液 → しゅう酸溶液 → 硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)溶液 → 硫酸四アンモニウムセリウム(Ⅳ)溶液 → しゅう酸ナトリウム溶液 炭酸ナトリウム → 塩酸 → 塩酸(メタノール溶媒) → 硫酸 → 水酸化カリウム・エタノール溶液 二クロム酸カリウム → 二クロム酸カリウム溶液 → 硫酸アンモニウム鉄(Ⅱ)溶液 → 硝酸二アンモニウムセリウム(Ⅳ)溶液 フタル酸水素カリウム → 過塩素酸(酢酸溶媒) → 酢酸ナトリウム溶液(酢酸溶媒) よう素酸カリウム → チオ硫酸ナトリウム溶液 → 臭素溶液 → よう素溶液 → 硫酸アンモニウム鉄(Ⅲ)溶液 → よう素酸カリウム溶液
-
-
生化学用試薬
-
従来の生化学研究では生体を構成する成分を化学物質としてとらえ、タンパク質や遺伝子等を構成するアミノ酸や核酸、さらにはペプチドやオリゴヌクレオチド、合成糖鎖等が試薬の基準に準拠した形で解析ツールとして使用されてきた。生体分子を認識する抗体やレクチン、精製タンパク質、培養細胞等生体から分離された物質も研究用の試薬の範疇として使用されていた。しかし生化学が医学や薬学と統合した「ライフサイエンス」へと拡張し、研究標的がより「生命」に密着したものになるのに伴い、生命倫理や環境、生態系への配慮、個人情報の保護など、これまでの自然科学研究にはあまりなかった独自の規制、制約がかかってきたのが現状である。
これまでの生化学研究試薬は生体成分の検出、同定、分析という視点から大まかに次のように分類されていたが、ここでは「ライフサイエンス」に重点を置き、生体由来試薬を再整理しておきたい。 (参考)これまでの生化学試薬の分類
・アミノ酸自動分析用試薬
・アミノ酸配列分析用試薬
・蛍光修飾用試薬(ラベル化剤)
・電気泳動用試薬
・ペプチド合成用試薬
・免疫研究用試薬
・遺伝子工学用試薬
・遺伝子検出用試薬
・細胞融合用試薬
・培養用試薬
・糖鎖工学用試薬
・その他(酵素精製用、ビタミン定量用など) -
タンパク質の検出-抗体試薬
-
タンパク質は生命のセントラルドグマの最終産物であり、生体における局在や構造、機能解析が生命現象の解明における最も重要な研究課題であった。分子生物学が発展し、タンパク質の詳細解析が進むようになった以前は、特定のタンパク質と特異的に反応する「抗体」が検出のための試薬として汎用されてきた。抗体は元来、生物の体内で異物が侵入したときにそれを排除するために産生されるものであり、医学の領域では侵入した病原体を排除する「免疫」のメカニズムが認識され、病原毒素を無毒化して動物に免疫して作られた「抗血清」は疾患の治療、診断などに応用されてきた。その後免疫を担う抗体分子である免疫グロブリン(IgG)が、タンパク質などの特定の分子(抗原)を認識し結合する構造と機能が明らかにされた。この性質を利用し、ヤギやウサギなどに特定の抗原を免疫して人工的に得られた抗血清が「ポリクローナル抗体試薬」として生体内におけるタンパク質の検出に応用されるようになり生化学分野の研究手法へと発展するに至ったのである。1970年代には単一の抗体産生細胞を細胞融合により自己増殖させ、単一の抗原を特異認識する抗体を動物の血清を用いずに生産する「モノクローナル抗体試薬」の作製技術が確立された。ペプチド合成や遺伝子組換えによるリコンビナントタンパク質の作製などによる抗原作製技術も飛躍的に向上し、より特異性、信頼度の高い抗体が試薬として多数開発、商品化された。また、ゲノムプロジェクトによってヒトゲノムの配列解析が完了し、そこから作られるタンパク質の機能、構造解析のニーズが増大し、そのマッピングを行うための網羅的な検出ツールとして、抗体試薬の占める重要度がますます高いものとなった。
(1)ポリクローナル抗体試薬
標的抗原をウサギ、ヤギなどの動物に投与し、免疫によって得られた血清(抗血清)を採取することで作製される。複数の抗体分子の混合体であり、標的抗原分子の様々な部位を認識し反応する(マルチエピトープ)。広い範囲の抗原部位を認識するため反応性が高く、また抗原抗体反応により凝集反応を起こしやすい特性を利用して、寒天ゲル内の沈降反応から可視的にタンパク質を検出する「免疫拡散法」などが古くから行われてきた。その後タンパク質の分離や標識などの技術が向上するに伴い、生体組織や細胞に標識した抗体を作用させて標的タンパク質を可視化する「免疫染色法」、電気泳動と抗原抗体反応を合わせてタンパク質を定性的に検出する「ウェスタンブロット法」、放射性同位元素や発色系の酵素を標識して放射活性、発色活性から目的タンパク質の定量を行う「ラジオイムノアッセイ法(RIA)」「エンザイムイムノアッセイ法(EIA)」などが応用され、ポリクローナル抗体は生体を構成するタンパク質の同定、構造や機能の解析に大きく貢献している。(2)モノクローナル抗体試薬
単一の抗体産生細胞に由来し、単一の抗原認識部位を有する抗体から成る。マウスなどの脾臓に抗原を免疫後、単一の抗体を産生するB細胞を取り出して骨髄腫細胞(ミエローマ)と融合することにより抗体産生融合細胞(ハイブリドーマ)を作製。特定の抗体を作り出す能力と継代的な増殖能を併せ持つハイブリドーマを培養またはマウスの腹腔内で安定的に産生させたものがモノクローナル抗体試薬である。ポリクローナル抗体が複数の抗体の混合物で、標的抗原の様々な部位を広い範囲で認識するのに対し、モノクローナル抗体は認識部位が単一であることから特異性が高く、より精度の高い分析に優れている。ハイブリドーマが樹立されれば同一の抗体を継代的に産生することが可能であるため、ポリクローナル抗体に見られた「ロット間差による性状のばらつき」、「交差反応性による非特異反応」という問題も大幅に解消された。表11─1にポリクローナル抗体、モノクローナル抗体それぞれの特性を示す。 ポリクローナル抗体とモノクローナル抗体の比較ポリクローナル抗体 モノクローナル抗体 由来 抗血清 ハイブリドーマ 免疫動物種 ウサギ、ヤギ、ヒツジ、モルモットなど マウス、ラット、ウサギ、ニワトリなど 生産コスト 低 高 生産技術 高度の技術は要さない 高度な専門技術を要する 作製期間 短期 長期間を要する 特異性 抗原上の複数のエピトープを認識し、多数の非特異抗体が含まれる 抗原上の単一のエピトープを認識し、すべて特異的な抗体である 製造再現性 ロットごとに抗体の組成は異なり、バラツキがある ハイブリドーマが同じであれば均一の抗体が産生され、ロット間差はない [アプリケーション]
-
a)免疫拡散法
- 抗原または抗体をアガロース等の支持体内で拡散させ、生じた沈降線を観察する方法。抗原抗体反応の有無や交差性を広範囲、定性的に確認できるのに加え、抗原抗体が支持体内で濃度勾配を生じ、適切な濃度になると沈降線を生じることから簡易な定量分析も可能である。
-
b)ウェスタンブロット(WB)法
- 複数のタンパク質を含む生体試料をアクリルアミドやアガロースを担体としたゲル内に可溶化して電気泳動で分離展開し、ニトロセルロース膜やPVDF 膜などに転写した後、抗体を反応させることでスポッティングし目的のタンパク質を検出する方法。抗体の特異性により夾雑な生体成分から特定のタンパク質を分子量依存的に検出できるのみならず、複数のエピトープの異なる抗体試薬を組み合わせることにより、酵素分解やメチル化、リン酸化などの翻訳後修飾といった動態などの解析も可能である。
-
c)イムノアッセイ法
- 抗原抗体反応の特異性を利用し、抗体に放射性同位元素や発色酵素、化学発光物質などを標識し、得られたシグナルの強度を測定することによって試料内の微量タンパク質を定量する方法。抗体の標識物質によって放射性同位元素を用いるラジオイムノアッセイ(RIA)法、発色酵素を用いたエンザイムイムノアッセイ(EIA)法、蛍光物質を用いた蛍光イムノアッセイ(FIA)法などがある。
-
d)エライザ(ELISA)法
- イムノアッセイ法の内、抗原あるいは抗体をプレートに固定化して標的物質と固相上で抗原抗体反応を行い、発色酵素によるシグナル強度で定量を行う方法をELISA 法と称する。定量法としては固相上に直接抗原を吸着させ、標識抗体を作用させる「直接吸着法」、エピトープの異なる種の抗体で標的物質を挟み込む「サンドウィッチ法」、競合反応によるシグナル強度の減少から定量を行う「競合法」がある。いずれの方法も既知濃度の標準物質のシグナル強度から得られた検量線をもとに、標的物質の濃度を推定算出して定量を行う。ELISA 法は生体成分中の微量タンパク質の検出、定量法として広く用いられているが、サンドウィッチ法により測定精度が向上し、抗体のエピトープ情報から機能・構造解析にも応用されるようになった。さらにハプテンによる抗原作製技術の拡張により、標的物質は薬物や環境物質、核酸分子などの非タンパク質系にも及んでいる。
-
e)エリスポット(ELISpot)法
- タンパク質を分泌する細胞を捕獲用抗体で固定化したプレート上で培養し、細胞除去後標識抗体を用いてスポッティングする方法。主にサイトカインなどの分泌型タンパク質の検出に用いられ、形成したスポットのサイズや発色強度により定量を行う。標的物質を分泌する細胞レベルで検出するため、血清など分泌後に希釈された環境下の検体を用いるELISA 法よりも遙かに測定感度が高いのが特徴である。スポットからの定量はエリスポットリーダーなどの専用機器を要する。
-
f)免疫染色法
- 解剖組織や細胞標本中の標的物質を直接可視化して検出する方法。標本中の標的物質(バイオマーカー等)の所在を確認できるだけではなく、複数の標識抗体を用いて「染め分け」することにより、マッピングを行うことも可能である。免疫染色法は一般にImmunostaining と呼ばれるが、組織を可視化する手技をImmunohistochemistry(IHC)、細胞を可視化する手技をImmunocytochemistry(ICC)と称し、特に前者は病理組織の染色など臨床診断やその研究に頻用されている。
-
g)免疫沈降法
- 抗原抗体反応によって免疫生成物が不溶化し、沈殿を生じる性質を利用した検出方法。Immunoprecipitation(IP)法と呼ばれる。標的物質に抗体を作用させて得られた沈殿を分離・回収し、精製および解析を行う。沈降しやすいポリクローナル抗体を直接作用させる他に、アガロースビーズや磁性粒子を結合させた抗体を用いることで回収効率を上げ、微量タンパク質の高度精製やタンパク質相互作用解析などより特異性の高い分析が行われるようになった。
-
h)中和抗体
- 酵素やサイトカイン、内分泌物質のような生理活性を有した物質の活性を中和、抑制する機能を持った抗体。活性の中和は標的物質の活性点や受容体の結合部位に抗体が結合してブロックすることによって行われ、タンパク質の生理機能や疾患のメカニズムの解明に効果を発揮する。特に認識部位が単一であるモノクローナル抗体においては、臨床や抗体医薬の分野への応用も期待されている。
-
タンパク質は生命のセントラルドグマの最終産物であり、生体における局在や構造、機能解析が生命現象の解明における最も重要な研究課題であった。分子生物学が発展し、タンパク質の詳細解析が進むようになった以前は、特定のタンパク質と特異的に反応する「抗体」が検出のための試薬として汎用されてきた。抗体は元来、生物の体内で異物が侵入したときにそれを排除するために産生されるものであり、医学の領域では侵入した病原体を排除する「免疫」のメカニズムが認識され、病原毒素を無毒化して動物に免疫して作られた「抗血清」は疾患の治療、診断などに応用されてきた。その後免疫を担う抗体分子である免疫グロブリン(IgG)が、タンパク質などの特定の分子(抗原)を認識し結合する構造と機能が明らかにされた。この性質を利用し、ヤギやウサギなどに特定の抗原を免疫して人工的に得られた抗血清が「ポリクローナル抗体試薬」として生体内におけるタンパク質の検出に応用されるようになり生化学分野の研究手法へと発展するに至ったのである。1970年代には単一の抗体産生細胞を細胞融合により自己増殖させ、単一の抗原を特異認識する抗体を動物の血清を用いずに生産する「モノクローナル抗体試薬」の作製技術が確立された。ペプチド合成や遺伝子組換えによるリコンビナントタンパク質の作製などによる抗原作製技術も飛躍的に向上し、より特異性、信頼度の高い抗体が試薬として多数開発、商品化された。また、ゲノムプロジェクトによってヒトゲノムの配列解析が完了し、そこから作られるタンパク質の機能、構造解析のニーズが増大し、そのマッピングを行うための網羅的な検出ツールとして、抗体試薬の占める重要度がますます高いものとなった。
-
タンパク質の作製-合成ペプチドとリコンビナントタンパク質
- タンパク質の基本構造は、アミノ酸が鎖状に多数連結したポリペプチドである。タンパク質を構成するアミノ酸は20種類で、片側のアミノ酸のカルボキシル基(─COOH)ともう一方のアミノ酸のアミノ基(─NH2)が脱水縮合し、その繰り返しによって長鎖ポリペプチドが形成される。タンパク質の基本構造は構成するアミノ酸の種類、配列順序が重要であり(一次構造)、自然界ではセントラルドグマの上流、即ち遺伝子の本体であるDNAの三塩基配列(三文字コドン)によって決定される。この長鎖ポリペプチドはフォールディングによる立体構造形成(αヘリックス、βシート)やドメイン・サブユニットの構築、さらにはリン酸化、メチル化等の翻訳後修飾により機能を発揮するが、その高次構造を決定する基本は構成するアミノ酸の配列である。 生化学の研究においては、生体成分からゲル濾過やアフィニティクロマトグラフィーを用いてタンパク質を分離・精製し、そこから構造や機能解析が行われてきた。20世紀半ばに固相合成法の開発によりペプチド合成の技術が向上すると、タンパク質のアミノ酸配列情報をもとに任意の配列を有した「合成ペプチド」が生理活性の抑制や抗体作製用の抗原として用いられるなど、タンパク質解析のツールとしてその発展に大きく貢献した。さらに遺伝子組換えによる形質転換技術の導入によって、生体におけるタンパク質生成の根幹であるDNA情報(cDNA)をベクターに導入して大腸菌などの宿主細胞内で発現させて得られた「リコンビナントタンパク質(組換えタンパク質)」が生産され、試薬としてのタンパク質の応用範囲が拡張された。その後、昆虫や哺乳動物を発現細胞に用いることでより生体由来に近い構造や機能を持ったタンパク質の生産も可能となった。さらに遺伝子解析によりゲノム中のDNA配列が明らかになると、その遺伝情報をもとにエンコードされるタンパク質のアミノ酸配列がライブラリ化され、ゲノム情報とタンパク質の構造・機能解析を包括した「プロテオーム解析」へと発展。遺伝情報からエンコードされる未知のタンパク質を生産したり、それらを認識する網羅的抗体を作製したりするなど、合成ペプチドやリコンビナントタンパク質のライフサイエンス研究における重要度は高まっている。
-
(1)合成ペプチド
- アミノ酸ユニットに適切な保護基を導入して目的の反応点のみを露出させ、脱水縮合によってペプチド結合を形成させる。液相法による合成では長鎖のペプチド合成は困難であったが、固相法の改良により、より長鎖のポリペプチド合成が可能となった。アミノ酸を改変することにより、メチル化やリン酸化ペプチドの合成なども行われるようになり、それらを抗原として抗体を作製することで、翻訳後修飾等を含むタンパク質の機能解析(ポストゲノム分野)にも大きく貢献している。環状ペプチドなど、特殊な構造を有するペプチドの合成も可能である。自動合成により合成効率が大幅に向上した一方で、合成鎖長に限界があり、またアミノ酸の配列や種類によって合成が不可能であるなどの技術的な限界も存在する。研究ツールとしては柔軟性もあり有用であるが、実際のタンパク質の構造や機能を再現することは不可能である。
-
(2)リコンビナントタンパク質
-
遺伝子組換え技術により、タンパク質をエンコードするDNA(テンプレートDNA)を発現細胞中に組み入れて、人為的に生産されたタンパク質を「リコンビナントタンパク質」という。
この技術によってタンパク質の大量生産が可能となり、ゲノムにおける遺伝子情報から生体内における微量タンパク質の網羅的な作製なども行われている。従来法ではテンプレートDNAを組み入れたベクターを発現細胞内で形質転換(トランスフェクション)した後に培養し、細胞を溶解して発現したタンパク質を抽出する方法がとられていた。発現細胞系としては培養が容易で増殖力が高く発現効率の良い大腸菌などの細菌細胞が用いられているが、真核生物が持つ翻訳後修飾や分子折りたたみなどの立体構造の再現が不可能なことから、昆虫や哺乳動物の細胞を用いたより高次的な発現も行われている。一方、これらの発現系は目的タンパク質の機能を再現できるというメリットがある反面、コストが高く収量性に乏しいというデメリットも存在する。近年は全細胞の抽出物からinvitroでより迅速簡便にタンパク質合成を行う「無細胞系」も導入され、早期に分解を受けやすいタンパク質作製にも対応できるようになった。
-
遺伝子組換え技術により、タンパク質をエンコードするDNA(テンプレートDNA)を発現細胞中に組み入れて、人為的に生産されたタンパク質を「リコンビナントタンパク質」という。
-
遺伝子解析、遺伝子操作-遺伝子工学研究ツール
- タンパク質を生産する設計図的な役割を果たしているのがゲノム中のDNAであるが、そのDNAを分離して人為的に操作し、細胞または生物に再導入する「遺伝子工学」の技術がライフサイエンスの研究において大きな転換期をもたらした。目的はDNAを発現細胞に組み入れて目的のタンパク質(リコンビナントタンパク質)を生産することにあり、制限酵素やDNAリガーゼ、発現のためのクローニングベクターなどが研究ツールとして用いられてきた。さらに細胞融合技術の向上やポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の導入により遺伝子の複製がより簡易に行われるようになり、遺伝子工学はバイオテクノロジーとして進歩を遂げ、遺伝子組換え作物やトランスジェニックマウスなどの遺伝子改変動物なども作製されるようになった。1990年代になると解析技術の飛躍的向上により、ゲノム中のDNA配列を決定するゲノムプロジェクトが進展。ヒトをはじめとする様々な生物の遺伝子情報がライブラリ化され、ゲノムの配列情報をもとに新薬の開発を行ったり、遺伝子治療の検討が行われるなど創薬、医療の分野へと応用範囲が広がることによってそれに伴う研究も盛んに行われている。21世紀になると部位特異的ヌクレアーゼを利用して特定のDNA配列を切断し、意図的なDNA改変を行う「ゲノム編集」技術が確立し、さらに可能性が拡張した。 遺伝子操作技術の進歩は研究を含めた近年のライフサイエンスに革命的な発展をもたらし、それに付随する試薬の役割も重要となった。一方で本来自然のものであった遺伝子情報を人為的に改変すること、ツールとしてウイルスや細菌などの感染源を用いること、また安全性の問題があることから生命倫理、環境、個人情報などへの最大限の配慮を要し、試薬においてもこうした規制の対象となる場合があることは留意する必要がある。
-
(1)ベクター
-
目的のDNAを導入するための「運び手」的な役割を担う核酸分子を「ベクター」という。
大腸菌の細胞内に存在する環状DNA分子、即ちプラスミド(自律増殖DNA)を改変した「プラスミドベクター」、細胞感染性を持つウイルスやファージを利用した「ウイルスベクター」などがある。ベクターは研究ツールとして単体、あるいは遺伝子導入やタンパク質発現キットのパーツとして試薬としても使用されている。プラスミドベクターは毒性が少なく、実験室レベルのタンパク質発現細胞株の樹立などに有用。またウイルス受容体を介して高い選択性と発現効率を持つウイルスベクターはより高度な遺伝子改変や遺伝子治療の研究にも応用されている。
-
目的のDNAを導入するための「運び手」的な役割を担う核酸分子を「ベクター」という。
-
(2)制限酵素
- 二本鎖DNAを特定の数塩基の配列を認識して切断する酵素(エンドヌクレアーゼ)。細菌に由来し、その種類によって切断する配列に特異性があるため、遺伝子のマッピングやDNA導入のためのプラスミド切断にも用いられるようになった。特異配列を認識する制限酵素は300種以上存在し、試薬としても幅広く利用されている。
-
(3)トランスフェクション
- DNAを細胞内に取り込ませる工程を「トランスフェクション」といい、核酸を取り込ませた脂質粒子(リポソーム)を用いた方法が主流であったが、電気パルスで細胞膜に穴を開けて取り込ませるエレクトロポレーション法、ガラスキャピラリーを用いてDNAを注入するマイクロインジェクション法、細胞感染性を持つウイルスベクターを作用させる手技などが開発され、導入する核酸や細胞の種類、用途によって多種多様の試薬が販売されている。
-
(4)ハイブリダイゼーション
- DNAの塩基が相補性を有することを用い、目的の塩基配列と相対する標識DNAを作用させて可視化することによって検出や同定を行うことができる。検出のために用いられる鋳型DNAはDNAプローブと呼ばれる。電気泳動により核酸成分を分離し、相補するDNAを検出する「サザン・ハイブリダイゼーション法」、RNAを検出する「ノーザン・ハイブリダイゼーション法」は古くから用いられている手法で、また細胞や組織を検体として検出を行うinsituハイブリダイゼーション法はウイルスや腫瘍組織の診断およびその研究にも応用され、生体中のmRNAの同定、検出にも有用である。20世紀末にはスライドグラス基板に様々な配列のプローブを固定し、ヒト細胞から抽出、調製した相補的DNA(cDNA)をハイブリダイゼーションさせることによって網羅的に大量解析を行う「DNAマイクロアレイ法」が開発され、ヒトをはじめとするゲノム解析プロジェクトに大きく貢献した。
-
(5)遺伝子の増幅(PCR)
- 特定の配列を有したDNA領域を、DNAポリメラーゼを用いて増幅させる方法を「PolymeraseChainReaction=PCR法」という。1980年代に耐熱性ポリメラーゼが応用、実用化されたことで、クローニングすることなしに迅速、簡便に目的DNAの増幅がルーチン化されるようになった。増幅を目的とする二本鎖DNAを熱変成させて一本鎖化し、そこに鋳型となるプライマーをアニーリングさせた後ポリメラーゼで伸長する。複製された二本鎖DNAを再び熱変成させ、操作を連鎖的に繰り返すことによって連鎖的にDNAを増幅させることが可能となる。ゲノム中の微量なDNAやRNAも増幅でき、さらに自動分析にも対応できることからゲノム情報の解析をはじめとする分子生物学の分野において必須の手法である。
-
(6)RNA干渉(RNAi)
- 相補性を有する二本鎖RNAがmRNAを特異的に分解する現象を「RNA干渉」といい、真核生物の遺伝子制御機構として発見された。このメカニズムを利用し、目的の遺伝子の発現を人工的な二本鎖RNAを作用させることで抑制する手法が開発され、ノックダウン実験などに応用されるようになった。約21─23塩基対からなる短鎖の二本鎖RNAをsiRNAといい、化学合成されたsiRNAでもRNA干渉を引き起こすことから、ゲノムプロジェクトと連動する形で任意の配列を持った遺伝子をノックダウンするsiRNA試薬がライブラリ的に使用されている。
-
(7)ゲノム編集
- DNAを切断する人工ヌクレアーゼを用い、特定の塩基配列をターゲットとして遺伝子を破壊したり(ノックアウト)置き換えたり(ノックイン)する技術を「ゲノム編集」という。用いられる人工ヌクレアーゼはジンクフィンガー(ZFN:第1世代)やTALEN(第2世代)、CRISPR/Cas9(第3世代)があり、世代とともに改変の自由度や効率、コストなどに改良が加えられている。ゲノム編集の技術は遺伝子の改変が容易に行えることもあって、遺伝子操作をテーマとした分子生物学の研究を格段に進歩させた。加えて農作物の品種改良(遺伝子組換え作物)等の産業分野や遺伝子治療等の医療分野へと可能性を拡大している。反面、生命の摂理ともいえる遺伝子の情報を人為的に書き換えるという行為自体は研究といえども倫理的な問題をはらんでいることは事実であり、特にヒト遺伝子の改変は法的に強い規制を受けている。
-
その他の生体由来関連試薬
-
(1)組織、血液等
- ライフサイエンスの研究においては、組織や血液等の検体を実際に用いて動態を解析するケースが多くあり、動物やヒトから採取した組織や血清、血漿等が「試薬」の範疇で使用されている。特定の生体成分の分離、抽出源として用いる他、抗体を用いた病理解析用の組織切片やアレイ、バイオマーカーのコントロール血清等の様々な用途で使用されるが、生体から直接分離された試薬はウイルスや病原体を含む可能性があるなど、通常の化学系試薬にはない「バイオハザード」のリスクがあるため、購入や取扱い、廃棄などには特別の配慮が必要な場合がある。またヒト由来の組織、検体については供給者の事前同意、即ち「インフォームド・コンセント」を得る必要があるなど、生命倫理上の制約も存在する。
-
(2)細胞
- 病態のメカニズムをはじめとする生命現象の解明には、そのモニターを行うために生体から分離、培養した細胞を用いてin vitro での実験が多く行われている。研究分野においても様々な組織から分離した「初代培養細胞」や遺伝子情報を導入して改変、継代を施した「株化細胞」などが生物学や分子生物学の基礎研究に用いられる他、タンパク質の機能解析や創薬化合物(リード化合物)の薬効作用をモニターするためのベースセルとして幅広く使用されている。再生医療の研究においては万能分化性を持つとされる「ES 細胞」や「iPS 細胞」の応用ニーズも急増した。細胞試薬はその機能を維持した「生きた」状態で使用される必要があることから、保存や輸送に細心の注意を払う必要がある。また遺伝子改変を施した株化細胞の中には環境拡散や安全性、生命倫理の規制を受けるものもある。
-
-
従来の生化学研究では生体を構成する成分を化学物質としてとらえ、タンパク質や遺伝子等を構成するアミノ酸や核酸、さらにはペプチドやオリゴヌクレオチド、合成糖鎖等が試薬の基準に準拠した形で解析ツールとして使用されてきた。生体分子を認識する抗体やレクチン、精製タンパク質、培養細胞等生体から分離された物質も研究用の試薬の範疇として使用されていた。しかし生化学が医学や薬学と統合した「ライフサイエンス」へと拡張し、研究標的がより「生命」に密着したものになるのに伴い、生命倫理や環境、生態系への配慮、個人情報の保護など、これまでの自然科学研究にはあまりなかった独自の規制、制約がかかってきたのが現状である。